 昭和あるある
昭和あるある 昭和を彩ったエリマキトカゲブームの真相に迫る
1984年、日本のエリマキトカゲブームは三菱CMから始まり、ユニークな姿が話題に。短命ながら昭和を象徴する文化現象として記憶されています。1984年CM 三菱自動車 ミラージュ 道は、星の数 エリマキトカゲ ACCグランプリ - YouTu...
 昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある 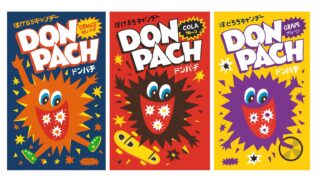 昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある 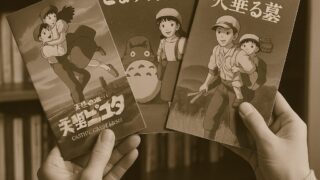 昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある  昭和あるある
昭和あるある